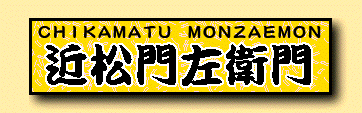
近松門左衛門は本名を杉森信盛といい、越前藩(福井県)の武士でした が、父が浪人したため京に上がり、公家に奉公しました。当時の公家は 徳川幕府に政治の実権を握られていましたから、けっして暮らしむきは 豊かでなく、したがって奉公人たちの給料も多くはありませんが、半面 では詩歌や歌舞などに通じた風流人が多く、四条河原町の歌舞伎役者や 浄瑠璃太夫の後継者も少なくありません。このような関係から生来文才 に長じていた近松は芸人との交際を結ぶようになり、浄瑠璃や歌舞伎の 筆を取るようになったと思われます。 近松の最初の浄瑠璃作品は天和三(1683)年宇治加賀壌のために書 いた『世継曽我』だとされますが、無著名の作はそれ以前にもかなり存 在すると考えられます。以降、近松はもっぱら加賀壌のために浄瑠璃を 書きました。そして貞亨三年にはじめて義太夫の頼みに応じて『出世景 清』を作ったのです。しかし近松と義太夫の結びつきは、そのままつづ いたわけではありません。作者としてようやく名声が聞こえ始めた近松 は、このころから歌舞伎脚本の執筆を手がけるようになりました。彼が 作品を提供したのは、当時京都の歌舞伎をせおって立つ名優、坂田藤十 郎でした。近松は藤十郎に歌舞伎脚本を提供しているあいだも、義太夫 のための浄瑠璃を書いてはいました。『松風村雨束帯鑑/まつかぜむら さめそくたいかがみ』『蝉丸/せみまる』など数多くありますが、いず れも古い題材をとった、いわゆる“時代物”ばかりでした。 そのころの浄瑠璃の内容は、初期の『十二段草子』などにくらべれば はるかに進んで戯曲性が濃くなり、叙情的な恋物語や怨霊物などもあり ましたが、まだまだ底流のは古めかし霊験談や武勇伝の要素が残ってい て、特に語りだしの文句「さてもそののち」と段末の「感ぜぬものこそ なかりけり」という定型が後生大事に守られていました。そして登場人 物の性格も類型的であり、文章もへたでした。 近松はまず人物を正確に描くことに力を入れ、文中の言葉使いも、武 士は武士らしく、公家は公家らしく感じさせる工夫をこらし、また悲し い場面をつづる場合でも、ただ文章で“悲しい”とか“哀れ”とか書く のでなく、聞く人が自然に涙を流すような状況の設定を心がけたのです 。このような作意は劇中の人物をいきいきとさせ、義太夫節の人気を高 めるのに力がありました。それでも時代物の場合は物語の内容が遠い昔 のことで、聴衆の共感にも限度がありました。 元禄十六(1703)年近松はついに現代の事件を浄瑠璃につくったの です。当時、大阪の話題をさらった曽根崎天神の森の情死を脚色した『 曽根崎心中』は“世話物”の第一作として歴史的に重要なだけでなく道 行の名文は国語の教科書にもとり入れられ、於生狙来(おぎゅうそらい /江戸中期の儒学者)が「近松の妙技ここにあり」と激賞したと伝えら れてます。 ここで、どうして近松が『曽根崎心中』を書くようになったかを考え てみましょう。近松はおそらくテーマを古い時代に求める時代物の執筆 にあきたりなかったと思います。しかし、徳川幕府の政策として時事問 題を脚色することはきびしく禁じられていました。 当時の社会は士・農・工・商という四民の階級制度が確立して、武家社 会がすべての規範になっていましたから、最も下層に扱われていた町人 の世界を扱うことで法の網をくぐり抜けようと思いついたにちがいあり ません。又、操り浄瑠璃の観客層は、まさしくその町人であり、流通経 済の発展にともなって着々と実力を貯えつつあった時期ですから、爆発 的な大あたりをしたのは当然すぎる結果だったのです。 山田庄一『文楽入門』参照
 |  |  |
